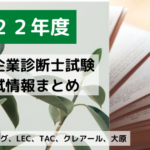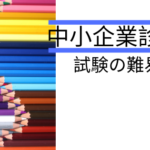平成30年度から、2次試験事例Ⅳの出題傾向が明らかに変わりました。
私は受験生時代、事例Ⅳを得点源にするという学習戦略を立てて、入念な対策をしていたのですが、出題傾向の変化のため、目論見は完全に外れてしまいました。
試験終了後、「これは完全に落ちた、、」と思いながらもある予備校の講師の方の講評動画を見ていたのですが、その講評動画では「設問で何を問いたいのかが分からず、答えが1つに絞れない」、「予備校でも会計士等の専門家が集まって、相談してやっと回答できるレベル。試験本番、受験生1人でどうにかできる問題ではない」等、なかなか辛辣なコメントをされていました。出題者が変わったのだろうという予測もされていました。
講評動画はこちらです。視聴するのにLECの会員登録は必要ですが、登録は無料です。
http://www.lec-jp.com/shindanshi/juken/2ji/sokuhou.html
この動画を見て、「もしかしたら受験生皆が満足に回答できず、部分点で案外良い点を取れてるんじゃないか」と少しの希望を持つことができました。
前置きが長くなってしまいましたが、平成31年度以降の受験生にとって、2次試験事例Ⅳ対策は大きな問題になるのではないかと思います。
少しでも受験生さんの助けになるようにこのページでは、対策情報を随時収集し、紹介していきたいと思います。
はじめに、過去の出題傾向についてまとめておきます。
事例Ⅳ過去(平成22~30年度)の出題傾向
過去の出題傾向をまとめると、以下のようになります。
- 問1は財務諸表を用いて経営分析をする問題
- 問4では年ごとに異なるテーマについて記述を求める問題
- 頻出論点は、CVP分析、CF(キャッシュフロー)計算、投資判断、期待値問題、WACC辺りに集約される
これらの頻出論点について解法パターンを身に付けるのには相応の時間がかかりますが、一方で出題範囲はかなり限定されているため、事例Ⅳはしっかりと対策をすれば得点源としやすい科目であると言われていました。
以下に、これまで事例Ⅳで出題された項目を列挙します。
|
平成30年度 問1、財務諸表を用いて経営分析 問2、CF計算、WACC 問3、CVP分析 問4、業務委託に関する記述問題 |
|
平成29年度 問1、財務諸表を用いて経営分析 問2、CVP分析 問3、CF(キャッシュフロー)計算、投資判断 問4、親会社、子会社に関する記述問題 |
|
平成28年度 問1、財務諸表を用いて経営分析 問2、CF計算、投資評価方法 問3、CVP分析(貢献利益問題) 問4、ネット予約システム導入に関する記述問題、CVP分析 |
|
平成27年度 問1、財務諸表を用いて経営分析 問2、損益計算書の作成、CVP分析、 問3、CF計算、投資判断 問4、大口顧客に関する記述問題 |
|
平成26年度 問1、財務諸表を用いて経営分析 問2、CF計算、投資判断 問3、CVP分析(プロダクトミックス、貢献利益問題) 問4、為替予約、オプション取引 |
|
平成25年度 問1、財務諸表を用いて経営分析 問2、CF計算 問3、生産に関するリスクについての記述問題 |
|
平成24年度 問1、損益計算書作成、財務諸表を用いて経営分析、投資判断 問2、CVP分析 問3、CF計算、WACC、事業承継に関する記述問題 |
|
平成23年度 問1、財務諸表を用いて経営分析、CF計算 問2、CVP分析 問3、CVP分析(プロダクトミックス、貢献利益問題) 問4、CF計算、期待値問題 |
|
平成22年度 問1、財務諸表を用いて経営分析 問2、CVP分析 問3、CF計算、投資判断 問4、債券に関する記述問題 |
平成30年度の新傾向
上記のまとめを見ると、一見、平成30年度も従来傾向を踏襲しているように見えます。確かに、出題された事項をひとことでまとめてしまえば従来通りと言えるでしょう。
しかし、実際に試験問題に取り組んで見るとこれまでの試験対策だけでは対応できないことが分かると思います。
これまでの出題のされ方は比較的パターン化されており、解法パターンを身に付ければ対応できる問題でした。また、対策のポイントになるのは、解法パターンを身に付けた上で、設問に合わせて解法パターンを応用できること、計算ミスをしないことでした。
それに対し、新傾向の特徴として、「回答を絞り込むための制約条件が不足していること」、「設問があいまいであること」というのがあります。この結果として、冒頭に書いたように、受験生は何を答えたら良いのかが分からない、答えを1つに絞れない、というよう状況になったのだと思います。また、身に付けた解法パターンを活かせる問題は少なく、計算については簡単なものしか出題されなかったという特徴もありました。
平成31年度以降の対策方針
まずは、従来通り解法パターンを身に付ける対策が必要だと思います。出題傾向が変わったと言っても、出題される項目自体には大きな変化はなかったためです。
また、平成30年度の結果を受け、次年度以降、再度従来傾向への回帰という可能性もあります。
加えて、制約条件が不足していたり、問われていることがあいまいな設問に対しての対策をする必要があります。これについては新傾向に対応した模試の受験や参考書の使用が1番良い方法でしょう。対策の一般論としては、回答する際に、自分の中で制約を決めながら答えていくというスタイルを身に付ける、ということも言えますが、それじゃああやふやで何をやって良いのか分からないですね。
ただ、現時点で新傾向に対応した参考書があるという話は聞いたことがありません。平成31年度の2次試験まではまだ時間があるため、予備校等でも対策検討中なのだと思います。良い情報を見つけたらこちらのページで紹介していきたいと思います。
以上のように、今後の受験生は、新傾向対策 + 従来傾向対策の学習が必要となり、これまでよりも事例Ⅳ対策の負担が増えることになると思います。しかし、どちらかの対策だけに絞るようなことはせず、しっかりと準備をしてもらいたいと思います。2次試験は、何点取ったら合格というものでなく、成績上位20%程度が合格の基準と言われています。優秀なライバル達との勝敗を分けるのは、こう言ったところで妥協せずに努力することだと思います。